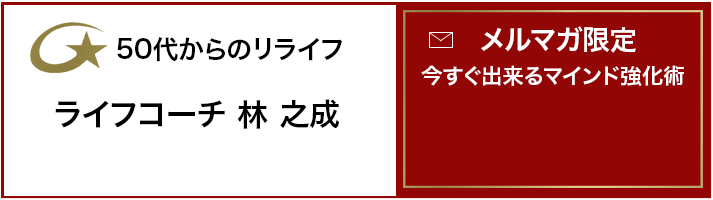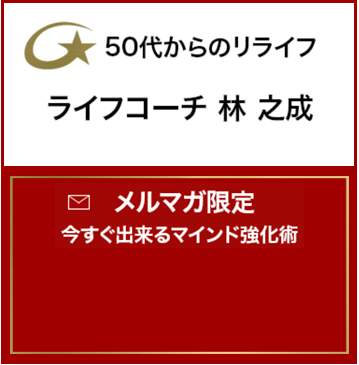電話: 080-5699-1961
mail: hayashi.kjin@gmail.com
今日は、日本の司法について。
この半年間、ある刑事裁判(1審)の傍聴に通っていたのですが、
先日、判決がおりました。
詳しい内容は、ここでは書きませんが、
半年にわたって弁護側は、
・起訴事由にかかわる有害性の科学的根拠を示すよう求め
・一方で、該当法律条文にかかる有害性が現代の科学あるいは情勢にあっておらず、かつ、被害者が存在せず、本件は被告人の基本的人権に抵触している
という論点で、その根拠を示してきました。
しかし、判決は、昭和時代の判例をもとに、
「その有害性は公知の事実であり」
というお決まりな表現とともに
実刑判決となりました。
(本件は、即、控訴手続きをとっています)
実刑判決を下すならば、論点に対する根拠について判断を示すべき、と傍聴人席にいる国民の一人である私は感じましたが、
こうした「条文に該当したら、有罪」という右から左のエスカレーター裁判を目の当たりにすると、いったい裁判官はなんのために存在するのか、と深い疑念が湧いてきます。
起訴=有罪
つまり
一審は(一審にかぎらないかもしれないのが恐ろしいところですが)
有罪・無罪を判断するのではなく、
起訴された事件に関しては結論ありきで刑を宣告する場(起訴されたらもはや罪人扱い)
あえていえば、執行猶予・情状酌量を計る場(つまり、どれだけ反省の色があるのかを見る場)
であり、
もっといえば
裁判官+検察官 対 被告人(弁護人)
という図式を実感しました。
なぜこうなるのか。
実は、日本は、国際人権規約の選択議定書に未批准なことがひとつの理由としてあげられます。
というか、こんな基本的なことを、今回の裁判まで私は知りませんでした。
これは、以下4点を意味します。
1. 個人通報制度が使えない
国連人権委員会(Human Rights Committee)などに対し、個人が自国政府を訴えることができません。
具体的には、第1選択議定書(ICCPR Optional Protocol I)を批准すると、
その国の国民は「自国の裁判で救済されなかった人権侵害」を国連人権委員会に直接通報できます。
しかし日本のように未批准だと、国際機関に訴えるルートが閉ざされている状態になります。
2. 死刑廃止に関する国際義務を負わない
ICCPRの第2選択議定書は「死刑の廃止」に関するものです。
未批准の場合、その国は国際的に「死刑を廃止する義務」を負いません。
たとえば、日本は死刑を存置しており、第2選択議定書を批准していません。
したがって国際的には「死刑廃止を約束していない国」として位置づけられます。
3. 国際的な信頼・人権評価への影響
未批准であること自体に法的な罰則はありませんが、
国際社会での「人権保護体制の信頼度」や「民主主義の成熟度」評価に影響します。
国連の人権理事会やEUなどでは、
選択議定書の批准状況を人権保障の指標として見ています。
そのため、批准していない国は「国際的な人権救済ルートを開いていない国」と見なされやすいです。
4. 国内的な影響:人権救済の範囲が国内法に限られる
選択議定書を批准していない国では、
人権侵害の最終的な救済が国内法に依存します。
つまり、裁判や行政救済で不当判決があっても、国際的に訴える手段がありません。
ちなみに、
第1選択議定書(個人通報制度)の批准国は約116カ国
第2選択議定書(死刑廃止を目的とするもの)の批准国は約92カ国
欧州の主要国は批准国ですが、
日本は双方に未批准です。
その他未批准国をあげるとすれば
アメリカ合衆国
イスラエル
といった国があげられます。
基本的人権の尊重・国民主権・平和主義を望む
民主主義国・日本の国民としては、
一度は議事(傍聴含む)や選挙に参加することが望ましいと私は思っていますが、
一度は、裁判所に足を運び、その目で見ることも大切です。
人数の制限がない限り、基本、傍聴は、自由に、誰でもできます。
2025年10月16日 17時22分